小林書店閉店の日。最後まで人に施す姿勢に、店の人生があらわれていた
小林書店が5月31日に閉店した。お昼からあった、お別れ会ならぬ「お礼の会」に伺った。 小林書店は72年続いた兵…

小林書店が5月31日に閉店した。お昼からあった、お別れ会ならぬ「お礼の会」に伺った。 小林書店は72年続いた兵…
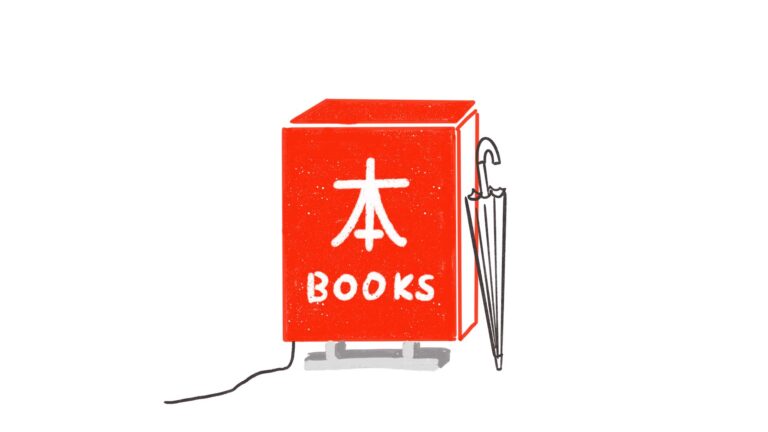
小林書店閉店の報せを受けて、店主・小林由美子さん含む12人で寄せた『文集 町の本屋』のあとがきを公開します。 …

兵庫県尼崎市立花で70年以上続いた新刊書店、「小林書店」が今月、2024年5月末で閉店されます。 そんな小林書…