作家キム・ヨンハのいうように、誰もがアーティストになるべき
ソーシャルゲーム『ブルーアーカイブ』統括ディレクターのキム・ヨンハ氏について調べようとGoogle検索したとこ…
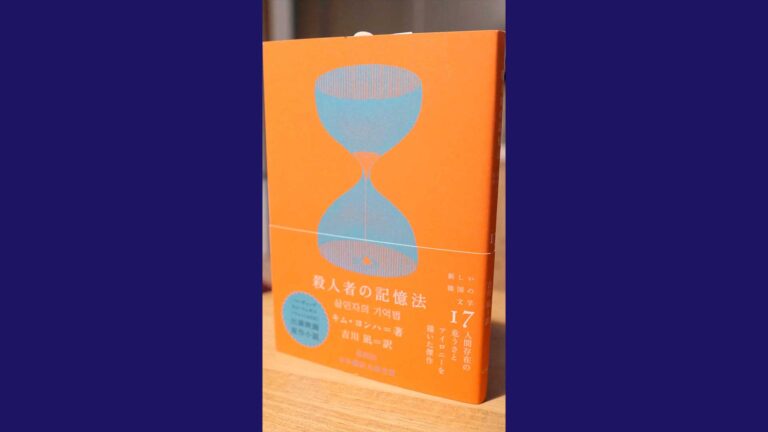
ソーシャルゲーム『ブルーアーカイブ』統括ディレクターのキム・ヨンハ氏について調べようとGoogle検索したとこ…

UnsplashのKen Whytockが撮影した写真 言葉にも鮮度がある。賞味期限がある。そして、言葉にでき…

個人的に衝撃的なニュースだったので書かざるを得ませんでした。兵庫県尼崎市・武庫之荘南口5分ぐらいにある喫茶店・…

先日、散髪に行ってきました。土日に予定が入ることが多いので、最近は平日の仕事の合間を見つけて行きます。そのたび…

小林書店が5月31日に閉店した。お昼からあった、お別れ会ならぬ「お礼の会」に伺った。 小林書店は72年続いた兵…
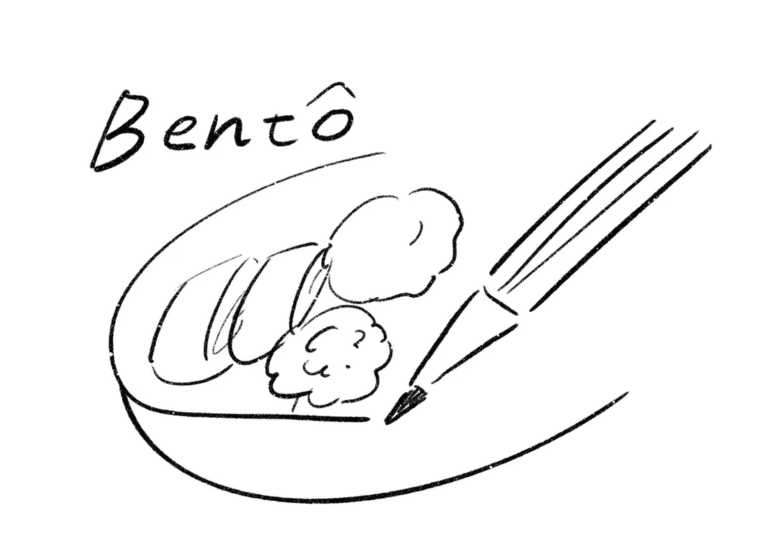
お小遣いをやりくりするために(そして健康のために)弁当を最近作っている。たいていは昨日の残りものにソーセージや…