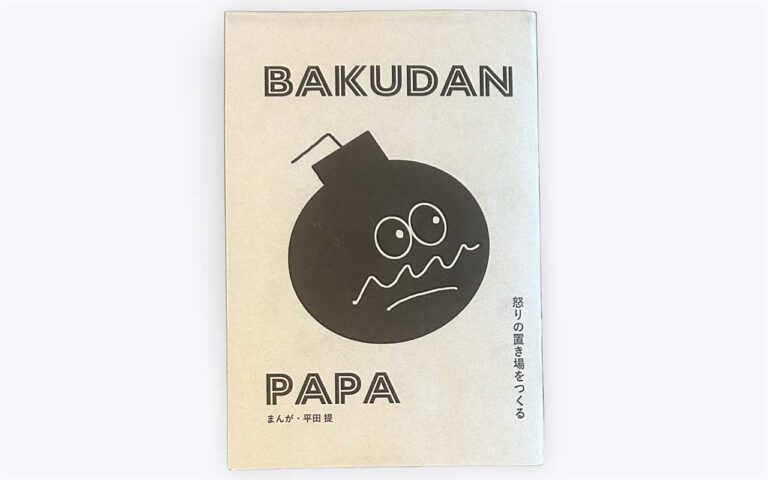『文集 町の本屋』あとがき

小林書店閉店の報せを受けて、店主・小林由美子さん含む12人で寄せた『文集 町の本屋』のあとがきを公開します。
※最終稿とは異なります。
あとがき
雨あがりのように、晴れやかな気持ちで町の本屋の旅立ちにはなむけを送りたい。この文集をそういう思いで綴った。
「まえがき」で若狭さんが書いてくださったように、この文集をまとめるきっかけは、尼崎市・立花にある小林書店さんの閉店を知ったからだ。小林書店を訪ねてお話したことがDIY BOOKSの大きな始まりだった。だから何かできないか、と考えた。
はじめから小林書店以外も含めた「町の本屋」のエピソードをテーマにしようと思っていた。というのも、後日店主の小林由美子さんと話して「そうして良かった」と感じたのだが、小林さんは涙の別れを望んでいないからだった(どうやったって小林さんもお客さんも泣くと思うんですけど)。むしろ「よくここまでがんばった!」と、自分で祝いたいと小林さんは言う。だから、最終日には紅白の布を飾りたいと。このZINEの表紙は小林書店の青いテントにちなんだ色合いにしようと思っていたが、この一言を聞いて「赤でいこう」となった。
誰しもにあるであろう、町の本屋の思い出。小林書店やうちのお店だけじゃなくて、全国のどこにでもあるはずの、小さなエピソード。たわいもない話かもしれない。でもそのたわいもなさは、その人の中にしかない。こうして文集にまとめなければ世に知られることがない話。少なくともあなたは読むことはなかった話。秘密。それをどうにか形にしたかった。
「店主が売りたい本を選ぶ」「本以外の雑貨を売る」「ビブリオバトルなどイベントで人を集める」など、小林書店はある意味いまの独立系書店の先駆的取り組みをしてきた。とはいえ『仕事で大切なことはすべて尼崎の小さな本屋で学んだ』(川上徹也/ポプラ社)にあるように、あるいは本書で由美子さんが書かれているように、小林書店がやってきたことは地道な、コツコツとした小さな仕事の積み重ねだ。新刊書店として大手取次との取引もずっと続いている。一方で、震災後に傘を売る取り組みを始めるなど新しい取り組みもどんどんやってきた。『キン肉マン』が大人気の時代、小さな書店にはほとんど配本されない。その時期に別の本で実績をつくることで大量に配本される実績をつくった。すべて小林書店が本と、お客さんと真摯に向き合ってきた結果だ。「特別ではない」なんて言えない。本屋をはじめて、同じことをまったくできないことが僕にはわかった。「まじめに商売をする」のがいかに難しいことか。それを続けてきた信用で、小林書店はできている。
僕はずっと思っていた。小林書店は町の本屋の象徴だと。町の本屋にできることをほとんどやってきた。それに、全国の本にかかわる人に慕われている。
長くなってしまったが、あえて小林書店以外も含む「町の本屋」全般をテーマにしたのはそれが理由だ。筆者によっては小林書店のことを書かれている方もいる。もちろんそれでいい。逆にそうじゃなかったとしても、どこかに小林さん夫妻の、小林書店にかかわる人たちの顔が見えてくるような気がするはずなのである。大切な本との出合いや、本屋にまつわる小さなお話が、小林書店と、それ以外の町の本屋ともリンクしていくんじゃないか。そう考えた。
表紙を傘のような本にしたのは、もちろん小林書店で傘が売られてきたことが一つの理由だ。もう一つは、本屋が、どこか雨やどりの場所のように思えるからだ。本屋をはじめてみたら、二時間、三時間話すお客さんがよく来られる。時間帯効果(利益)を考えると非常に大変にあれではあるが、偶然聞くお話はとても面白い。一方で、自分の店がお寺や教会のように思えてくる。おこがましいけど。
自分がお客さんとして本屋に行くときは、ただ暇だとか、進路に迷っただとか、どこか落ち着く場所を探して訪れていた気がする。僕にとっても、本屋は教会のような存在だった。
本屋は、人生の雨やどりの場所なんだと思う。
だからこそ、小林書店の最後の日は、終わりというよりは旅立ちのようにとらえたい。

『大辞林』を引くと「本屋」にはこういう意味がある。
【本屋(ほんや)】本を売る店、また人。出版社をいうこともある。書店。書肆(しょし)。
全国でいろんな町の本屋が試行錯誤している。大変だけど、面白い時期だ。
僕らDIY BOOKSも原稿を書き、店内にあるリソグラフで印刷して手で製本して売る、町の中華みたいな本屋だ。本屋一本では無理だけど、やりがいはある。
一方で、今の時代、ほとんどの人がすでに本屋になりかけているんじゃないかと思う。
文学フリマやアートブックフェア、コミティア、コミックマーケットはいわずもがな、同人誌やZINE界隈は盛り上がっている。
上の定義からいけば、自分でZINEをつくってイベントで手売りする人は、もれなく本屋であろう。真っ当な意味で。メルカリで本を売るために売り文句を考える人も、本屋だと思う。
本屋は減っているけれど、町にはたくさんの本屋さんが歩いているはずなのだ。
現「町の本屋」としてすべきことは、町にいる「本屋予備軍」に声をかけ、本屋になってもらうことだ。うちの店も、仕入れて本を売るというより、いろんな人に本をつくってもらいたくて開いた。
だから僕は言いたい。あなたが本屋になるんだよ、と。いや、すでにあなたは本屋なので自覚してください、と。
小林書店や、多くの町の本屋からのバトンをみんなで笑顔で受け取って、新しい本屋を続けていく。またつらくなったら、傘を閉じて本屋で雨やどりすればいい。町の本屋さんはそのときに寄り添う本を、そっと置いていてくれているはずだ。
町の本屋さん、ありがとう。また会いましょう。