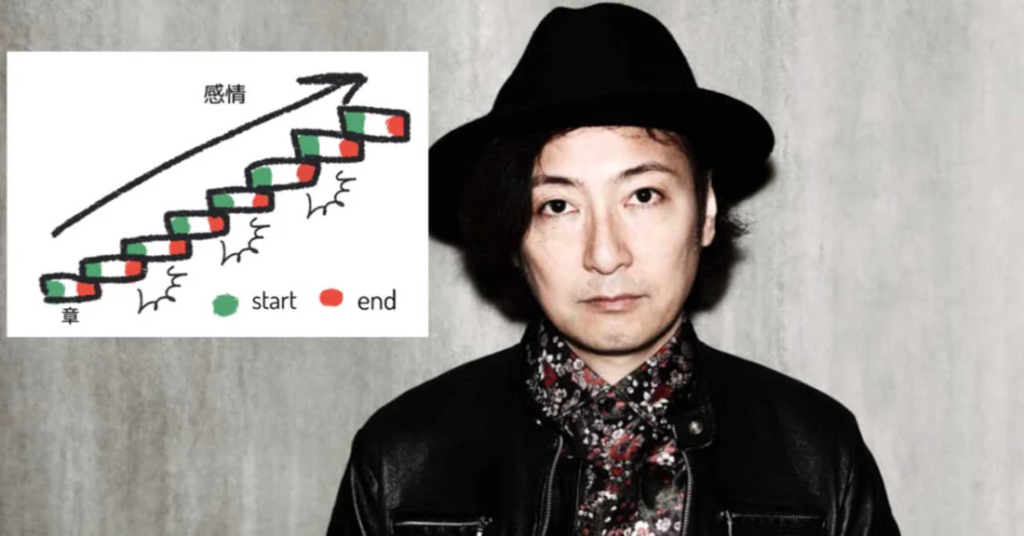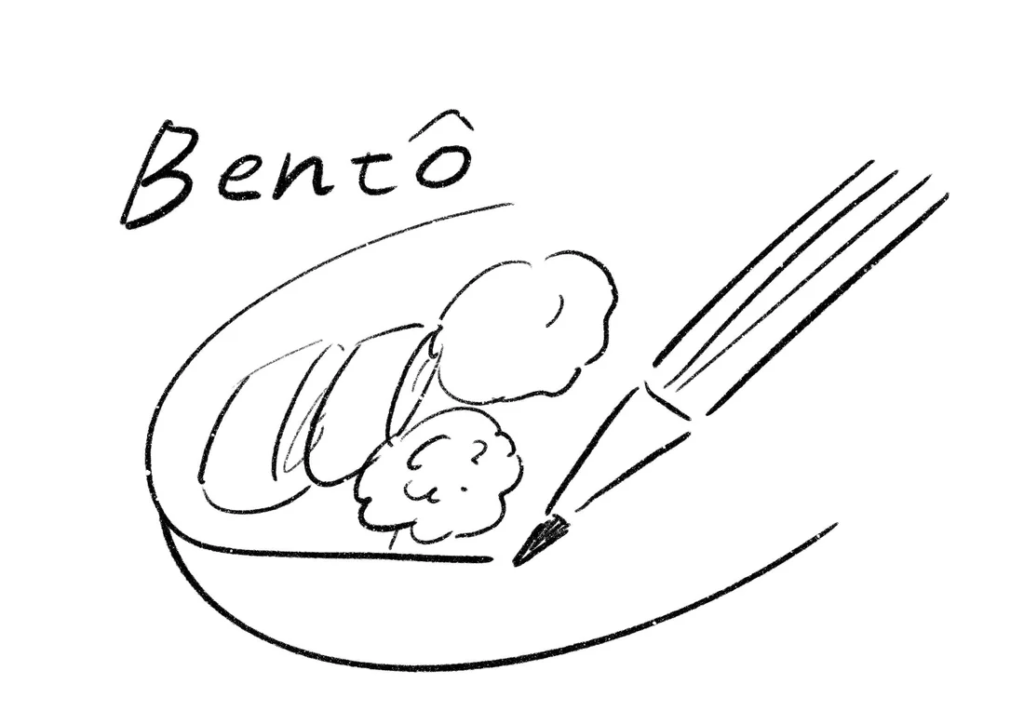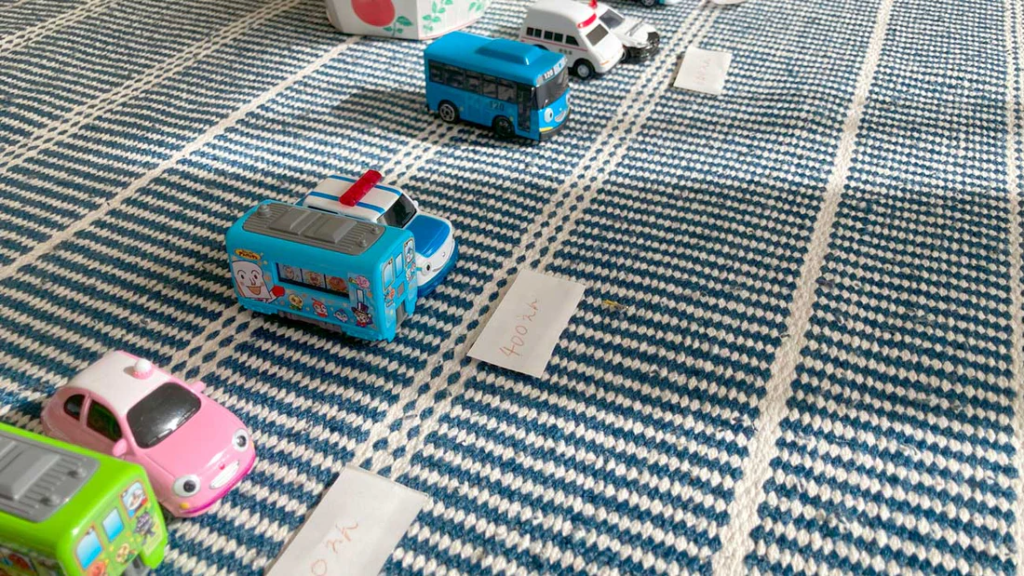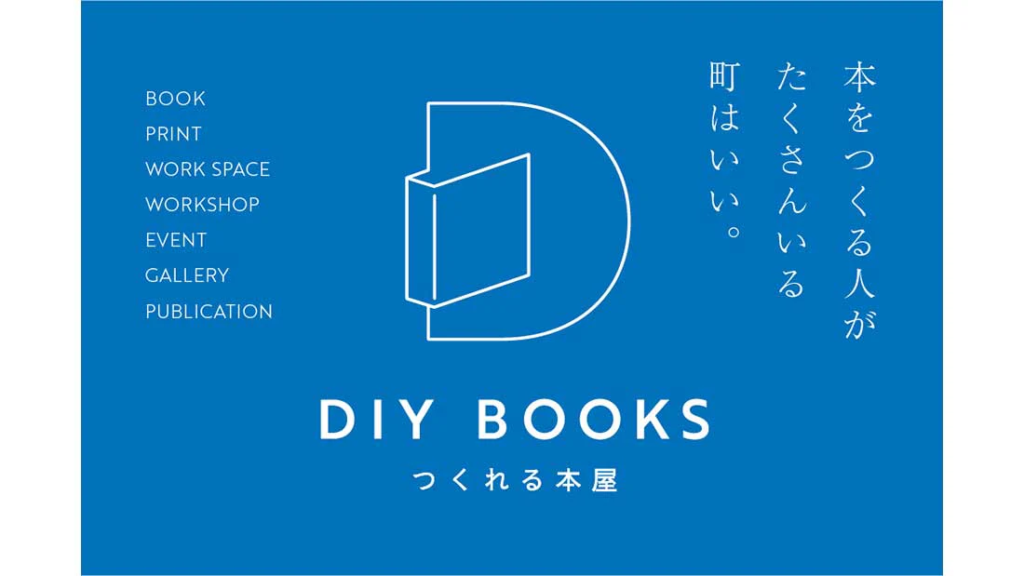DIY BOOKSで「うるし継ぎレッスン」がはじまります。
「金継ぎ」は最近、海外でも「KINTSUGI」として知られていますよね。欠けた器を直して使い続ける考え方込みで、じわじわと興味を持つ方が増えていることを実感します(金継ぎ関連書籍も多くなってきました)。
僕は知らなかったのですが、金継ぎの「金」って最後の仕上げに使われるものだったんですね。
多くの場合はエポキシ樹脂、パテなどでつないでいく。金を使用しない場合でも「金継ぎ」と呼ばれる。
ただ今回は、プラスチック樹脂ではなく、自然由来のうるしを使用した「うるし継ぎ」です。仕上げには金を使用しません。
講師は、DIY BOOKSにたまたま来ていただいた佐藤由輝さん。うるし作家と知り、ワークショップをお願いしたいとお話していたのが実現しました。
このレッスンは6~9月まで全6回で欠けたり割れたりした器をゆっくりとうるしで直していきます。
ゆっくり時間をかけてモノを直していく楽しみをぜひ味わってみてください。
概要
会場:DIY BOOKS(兵庫県尼崎市武庫元町1-27-5)
日程:全8回
2024年6月6日(木)~9月26日(木)の隔週木曜日
対象:すべてのレッスンに参加可能な方
定員:6名×2クラス
同日に別時間帯で2クラスあります。いずれかの時間帯をお選びください。
①12:30~14:00
②14:30~16:00
参加費:28,000円(材料費含む)
持ち物:以下の持ち物を持参ください。
- 割れや欠けのあるある陶磁器2、3点(ガラス不可)
- 保管用段ボール箱(D40×W30×H20ほど)
- ハサミ
- カッター
- 古布
- 割り箸(複数本)
- エプロン、腕カバーなど
※当日は汚れてもいい服装でお越しください。
注意事項
※本漆を使用するため、手などがかぶれる可能性があります。かぶれにくいよう講座の中でも注意換気を改めていたしますが、あらかじめご了承ください。
※修繕後の陶磁器は、直火・電子レンジでの使用はできません。
【お申し込みはこちらから】